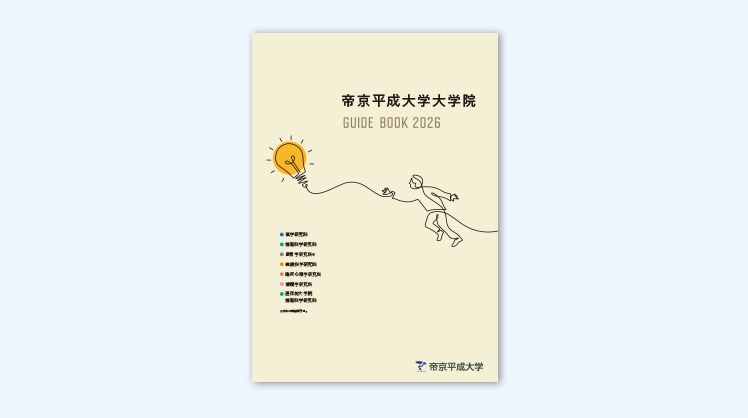健康科学研究科 健康栄養学専攻(修士課程)・健康科学専攻 健康栄養学分野(博士課程)


“食・栄養・健康”に関するスペシャリスト、
リーダー及び教育者・研究者を養成します
健康科学研究科 健康栄養学専攻修士課程
本専攻の教育目標は、食・栄養・健康に関する高度な専門的知識を修得し、それらを応用して現状を分析、諸問題を抽出解析してその解決策を見いだし、さらに実践する能力を養うことにあります。これらを通して“食・栄養・健康”のスペシャリスト、管理栄養士のリーダー、教育者・研究者、食品関連業界の研究者などを養成することを目指しています。
近年、生活習慣病の増加、食の安全への不安、食文化の喪失など、食や栄養、健康に関する問題が深刻になっています。また、加速する高齢化社会において、いかに健康寿命を延ばすか、そのためのサルコペニア、フレイル対策なども喫緊の課題で、医食同源の重要性があらためて認識されています。これらの問題に対応するため、食育基本法の制定・実践や栄養教諭の普及など国を挙げての取り組みがなされています。また、医療現場では、あらゆる疾病治療において、栄養がその基礎となることの認識も深まっており、多職種によるチーム医療の実践が求められ、Nutrition Support Team(NST)では管理栄養士が主導的な役割を果たすことが期待されています。さらに、一般社会での機能食品や栄養補助食品の普及は目覚ましく、機能性食品などを適切に利用するための栄養学的知識の普及も必要とされています。食の安全も重要な課題です。このように、栄養の専門家に対する社会のニーズは非常に高くなっています。本専攻はこのような社会のニーズに応える人材を養成します。
健康科学研究科 健康栄養学専攻(修士課程)のメリット
健康科学研究科 健康栄養学専攻(修士課程)では、「一般教育訓練給付金制度」の対象として、指定を受けています。
健康科学研究科 健康科学専攻健康栄養学分野(博士課程)
健康栄養学分野では、修士課程で修得した“栄養・食に関する課題設定・問題解決・成果発表能力”をより高度なレベルに高める教育を行います。また、このような問題解決には関連職種の専門家との協力が不可欠です。関連の専門家と協力して研究を行う経験を積んで、真のコミュニケーション能力を培います。さらに、英語論文を積極的に読む習慣を修得し、英語の読解力・発表能力を身につけ、国際的に活躍できるように支援します。これらを通して、栄養・食の領域で指導者として活躍できる能力を養成します。
健康科学研究科 健康科学専攻(博士課程)のメリット
健康科学研究科 健康科学専攻(博士課程)では、「一般教育訓練給付金制度」の対象として、指定を受けています。
専攻長からのメッセージ
健康の基盤である栄養に関する専門家、リーダーを養成
―問題を見いだし科学的に解決する能力を養います

本専攻では、健康であるために最も重要な基盤となる食や栄養に関する専門家の養成を目指しています。この過程においては、まず現在まで分かっているエビデンスを確認し、その上で何が問題かを見いだすこと、そしてそれを科学的にいかに解決してゆくかの思考回路を形成することが最も大切です。このようなことは、専攻科学生が、将来、栄養学のいかなる領域においても、リーダー格となるために役立つものと考えられます。
指導教員は基礎栄養学、臨床栄養学、食品学をはじめとした様々な専門領域を有し、国際的にも活躍しておりますので、専攻科学生は自身の希望に応じて、関心のある領域を選び、研究することができます。教員は自らの実績を活かして、学生一人ひとりの研究テーマに即したきめ細かな指導を行いますので、着実に研究成果を上げることが期待できます。楽しく、かつ切磋琢磨して研究することをモットーにしています。また就職支援をはじめとして卒業後も継続的な支援を行います。
特色
多職種からなり幅広い専門分野を持つ教員による指導で多彩な研究に対応
食・栄養・健康の研究では、関連分野の専門家との協力が欠かせません。本専攻の教員は、臨床医師(消化器外科専門医)、管理栄養士、薬剤師、看護師の資格を有する者や、解剖学、生物科学、免疫学、脳神経学、農芸化学、水産学などを専門とする者で構成されており多彩です。またグループ校である帝京大学の医学部をはじめ、東京大学農学部やいくつかの食品企業とも共同研究を行っています。従って、本専攻で学ぶことにより、関連分野の専門知識の修得やその専門家と協力する能力を身につけることができるようになります。
社会のニーズに応える食・栄養・健康に関する課題解決能力を養成
教員は、病院における栄養治療やNutritional Support Team(NST)活動、高齢者の栄養管理、健康食品開発、行政での栄養教育、食品分析、厚生労働省委託研究など、近年の大きな社会的課題に関して優れた研究実績と実務経験を有しています。これらの実績と経験を活かし、学生に対して社会のニーズを読み取る能力、社会のニーズに応える課題解決能力を養成します。
課程修了の認定及び学位
健康科学研究科 健康栄養学専攻(修士課程)
| 課程 | 修士 |
|---|---|
| 在学期間 | 2年以上4年以下 |
| 修得単位及び条件 |
|
| 学位 | 修士(健康科学) |
健康科学研究科 健康科学専攻 健康栄養学分野(博士課程)
| 課程 | 博士 |
|---|---|
| 在学期間 | 3年以上6年以下 |
| 修得単位及び条件 |
|
| 学位 | 博士(健康科学) |
教育研究及び担当教員
※担当教員、研究指導内容等は変更になる場合があります。
健康科学研究科 健康栄養学専攻(修士課程)
臨床栄養学
教授 福島 亮治
栄養はあらゆる疾病治療の基礎となるものです。いかなる高度な治療技術も栄養状態が悪ければ十分な効果を得ることはできません。疾病の病態を詳細に把握し、それに即した適切な栄養治療を行うことが極めて重要です。各種疾病に関する高度な専門知識を深め、栄養治療に関する最新の知見を身につけ、課題に対して研究することで、栄養治療に関する問題解決能力を養成します。
健康管理学
教授 牟田 真理子
日本人の三大死因の1つのがんは食習慣などの生活習慣が関係しています。がんを予防するための食生活について文献検索し、がん患者の生活の実態を調査し、栄養や食事の面からがんを予防する方法を検討し、健康の維持管理について研究します。また、がん患者の治療中の食事摂取や栄養摂取状況について調査し、治療中のがん患者の健康状態の向上について検討します。
応用栄養学
教授 野口 律奈
主に、以下の課題に対する研究、及び研究結果を現場で活かす力を養います。
- うつ病患者の栄養的課題
- うつ病患者のリハビリテーションとしての調理実習の活用
- 高齢者のフレイルと栄養・調理
- 災害時の栄養課題
- ナトカリ比を活用した地域の高血圧予防
食品メタボロミクス
教授 前田 竜郎
食品の2次機能である美味しさや食べる喜びなどは、ヒトが五感で感じるにおい(香り)、呈味、食感、色調、外観、組織構造、咀嚼音などの品質特性は最新の科学的な分析機器を活用して評価を行っている。この中でもノンターゲティングオミクスを用いたにおいや呈味の網羅的解析により新たな食品の風味の品質特性のプロファイル解析や新規化合物探索が可能である。食品から得られた風味に関する網羅的解析データは多変量解析を始めとしたインフォマティクスにより、食品の品質を革新的に高めるために活用し、新規なフレーバーの解明により生活の質(QOL)の向上に寄与できるような新たな技術開発に取り組んでいます。
食品作用学
教授 丸山 奈保
ハーブやスパイスは、古来より、抗菌作用や防腐作用を目的として経験的に使用されていました。近年、これら植物およびその成分・抽出物の多くは、抗炎症作用や抗感染作用などを有し、生体防御系にも深く関与していることが科学的に明らかになってきています。ハーブやスパイスが微生物にどのように作用するのか、私たちの生体防御系にどのように影響を与えるのかに関して、伝統的な使用方法との比較も行いつつ、国内外の論文を調べ、考察し、今後の可能性について研究します。
栄養管理学
准教授 髙橋 寛子
人体の栄養状態を適正に保つことは、疾病の予防、治癒、重症化予防、介護予防に貢献しますが、傷病者、要支援・要介護者は栄養状態を良好に保つことが困難なことがあります。そこで、その阻害要因を明らかにし、人々の健康とQOL向上に寄与できる栄養管理法や食環境整備の方法を研究します。
生命科学
准教授 水谷 晃子
本研究では、免疫応答の中核を担うヒト白血球抗原(HLA)の多型に着目し、その機能的意義を分子・細胞レベルで解明することを目的とします。HLA遺伝子は多様性に富み、免疫応答や疾患感受性、移植適合性などに深く関わることから、NGS法や培養細胞実験系を活用し、特定のHLAアリルが免疫機能に与える影響を解析します。本研究を通じて、個別化医療の基盤となる遺伝学の理解を深めるとともに、自己免疫疾患や感染症分野への応用を目指します。
分子生理学
准教授 長谷川 和哉
栄養、運動、ストレス、疾病といった生体内外からの刺激に対する応答は、遺伝子、タンパク質、代謝物といった分子レベルの変動によって制御されています。網羅的遺伝子発現解析(RNA-seq)や質量分析計によるメタボロミクスといったオミクス技術と、細胞を用いた機能評価系を組み合わせることで、これらの生体分子の動態を多角的に捉えます。これにより、アスリートの急速減量時における生体応答メカニズムの解明や、体内で産生される揮発性有機化合物の網羅的解析、機能未知なオーファン受容体が関わる新規情報伝達系の探索といったテーマに取り組みます。こうした研究を通じて、科学的根拠に基づいた問題解決能力と独創的な研究発想力を養います。
給食経営管理学
講師 野原 健吾
管理栄養士・栄養士の固有の業務は「栄養の指導」であり、その一環として、給食施設では、特定多数の人々を対象に適切な栄養管理を実施することが求められます。そこで、適切な栄養管理を行うための前提となる栄養評価や食事管理に関する研究を行います。さらに、給食施設における食事の品質管理や生産管理についても、栄養管理の視点を踏まえて探究し、給食施設における栄養管理に関する課題解決能力を養います。
健康科学研究科 健康科学専攻 健康栄養学分野(博士課程)
臨床栄養学
教授 博士(医学) 福島亮治
栄養はあらゆる疾病治療の基礎となるものです。いかなる高度な治療技術も栄養状態が悪ければ十分な効果を得ることはできません。疾病の病態を詳細に把握し、それに即した適切な栄養治療を行うことが極めて重要です。各種栄養治療は国や地域、その文化的背景などで多少ことなることもありますが、各種疾病に関する世界の栄養治療の最新の知見を検索し、課題に対して研究することで、栄養治療に関する問題解決能力を養成します。
健康管理学
教授 博士(薬学) 牟田 真理子
日本人の三大死因の1つのがんは食習慣などの生活習慣が関係しています。がんを予防するための食生活について文献検索し、がん患者の生活の実態を調査し、栄養や食事の面からがんを予防する方法を検討し、健康の維持管理について研究します。また、がん患者の治療中の食事摂取や栄養摂取状況について調査し、治療中のがん患者の健康状態の向上について検討します。
応用栄養学
教授 博士(栄養学) 野口 律奈
主に、以下の課題に対し、文献を調べ、問題解決のための研究をし、その成果を学会及び論文で発表する力を培います。
- うつ病患者の栄養的課題
- うつ病患者のリハビリテーションとしての調理実習の活用
- 高齢者のフレイルと栄養・調理
- 災害時の栄養課題
- ナトカリ比を活用した地域の高血圧予防
食品メタボロミクス
教授 博士(農学) 前田 竜郎
食品の2次機能である美味しさや食べる喜びなどは、ヒトが五感で感じるにおい(香り)、呈味、食感、色調、外観、組織構造、咀嚼音などの品質特性は最新の科学的な分析機器を活用して評価を行っている。この中でもノンターゲティングオミクスを用いたにおいや呈味の網羅的解析により新たな食品の風味の品質特性のプロファイル解析や新規化合物探索が可能である。食品から得られた風味に関する網羅的解析データは多変量解析を始めとしたインフォマティクスにより、食品の品質を革新的に高めるために活用し、新規なフレーバーの解明により生活の質(QOL)の向上に寄与できるような新たな技術開発に取り組んでいます。
食品作用学
教授 博士(薬学) 丸山 奈保
ハーブやスパイスは、古来より、抗菌作用や防腐作用を目的として経験的に使用されていました。近年、これら植物およびその成分・抽出物の多くは、抗炎症作用や抗感染作用などを有し、生体防御系にも深く関与していることが科学的に明らかになってきています。ハーブやスパイスが微生物にどのように作用するのか、私たちの生体防御系にどのように影響を与えるのかに関して、伝統的な使用方法との比較も行いつつ、国内外の論文を調べ、考察し、今後の可能性について研究します。
生命科学
准教授 博士(医学) 水谷 晃子
本研究では、免疫応答の中核を担うヒト白血球抗原(HLA)の多型に着目し、その機能的意義を分子・細胞レベルで解明することを目的とします。HLA遺伝子は多様性に富み、免疫応答や疾患感受性、移植適合性などに深く関わることから、NGS法や培養細胞実験系を活用し、特定のHLAアリルが免疫機能に与える影響を解析します。本研究を通じて、個別化医療の基盤となる遺伝学の理解を深めるとともに、自己免疫疾患や感染症分野への応用を目指します。
分子生理学
准教授 博士(医学) 長谷川 和哉
栄養、運動、ストレス、疾病といった生体内外からの刺激に対する応答は、遺伝子、タンパク質、代謝物といった分子レベルの変動によって制御されています。網羅的遺伝子発現解析(RNA-seq)や質量分析計によるメタボロミクスといったオミクス技術と、細胞を用いた機能評価系を組み合わせることで、これらの生体分子の動態を多角的に捉えます。これにより、アスリートの急速減量時における生体応答メカニズムの解明や、体内で産生される揮発性有機化合物の網羅的解析、機能未知なオーファン受容体が関わる新規情報伝達系の探索といったテーマに取り組みます。こうした研究を通じて、科学的根拠に基づいた問題解決能力と独創的な研究発想力を養います。
授業科目の概要
※授業科目等は変更になる場合があります。
健康科学研究科 修士課程 全専攻共通
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学研究法特論Ⅰ | 健康科学分野、特に臨床における研究の意義と研究論文作成の一連のプロセスを理解し、高度専門職としての実践に貢献する研究方法論を学修することで、専門演習や特別研究を実施するための基礎を作る。具体的には、保健や医療領域における具体的研究例を学ぶことを通して、研究計画の立案、データ収集と分析、研究成果のまとめ方に関する知識・技術を養う。 |
| 健康科学研究法特論Ⅱ | 院生各自の具体的な研究方法は「健康科学特別研究」で研究指導教員から学ぶことになっている。しかし、異なる研究分野における研究手法など、自分の研究では学修できないような研究内容を知ることも必要である。このような観点から、本科目は「健康科学研究法特論Ⅰ」に続く共通科目として設定し、健康科学分野の研究方法と研究論⽂作成のプロセスをより深く理解し、習熟することを到達目標とする。具体的な研究例を学ぶことを通して、研究計画の⽴案、データ収集と分析、研究成果のまとめ⽅、およびプレゼンテーションに関する知識とスキルを身に付ける。 |
| 医療統計学特論 | 科学的根拠に基づく医療(Evidence-Based Medicine:EBM)を実現させるために様々な研究が行われており、その結果を判断する上で統計学はとても重要な役割を果たしている。そのため研究デザインの段階で得られるデータの性質や解析手法をきちんと考え決めておく必要がある。本講義では、統計学におけるデータ解析の基礎的な内容から始まり、主要な統計手法について講義を行い、修士・博士課程での研究における統計処理をSPSSを用いて実践する内容とする。 |
| 医療教育学特論 | 保健医療専門職として、後進育成のために必要な教育学に関する基礎的知識と教育方法を学ぶことが目的である。また、現在の保健医療福祉領域で課題となる多重問題ケースに対応するために多職種連携教育・協働について学び、リーダーシップを担うべく知識と技術の基盤を修得することも目的とする。 |
| 保健医療管理学特論 | 保健や医療サービスシステムの現状を把握するとともに保健医療に携わる医療関連職種が直面している課題について討議し、サービスシステムを説明し課題を明らかにすることができるようにする。患者ケアシステムを実行する上で不可欠なマネージメントを学び、専門的知識・技術を有効に活用できる能力を養う。他職種の医療サービスシステムを学ぶことで他職種連携についての理解を深め、多職種協働の実践に役立てる。 |
| 健康医科学特論 | 臨床現場で関わる傷病・疾患は各医療専門職により異なる。しかし、罹患率の高い生活習慣病などに関する知識は、すべての医療専門職に必要である。疾病予防や健康維持の観点からは、成長期や青年期の健康医学の理解も重要である。臨床医学分野の最新の知識を学ぶことは、自らの生涯学習として有用なだけでなく、専門職として接する患者や家族の状況を理解し、専門的判断を構築する際に役立つと思われる。 到達目標:臨床医学一般についての知識を広げ、深めることを目標とする。 |
| 医科学英語特論 | 科学的研究分野で使われる英語や医療英語は、一般的英語と異なる点がある。英会話を含め一般的英語が得意な人でも、医療や研究分野の専門英語に慣れる必要がある。専門職業人や教育者、特に研究者をめざす大学院修士課程の院生にとって、専門分野の英語文の読解や作成能力は将来必要な基礎学力である。 到達目標:この授業では、健康科学や医学医療分野の英文読解力を向上させることを主目標とする。 |
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学特別研究 | 指導教員の指導下で修士研究を行い修士論文を作成する研究科目である。2年間の概略は次の通りである。 【1年目】実施予定の研究に関する情報集積を行い、研究の目的と方法を明確にし、研究計画を作成する。研究倫理を理解し、研究倫理教育のコースを修了する。倫理審査の承認後、研究を開始する。 【2年目】研究計画に基づいて研究を遂行し、修士論文を完成させる。研究が計画に沿って進んでいることを確認し、研究結果を分析し考察を行う。研究テーマや研究方法の変更が必要になった場合は、速やかに研究計画を修正する。倫理審査申請書類の再提出など必要な手続きを行う。 到達目標:研究倫理を理解し、倫理審査申請書類の作成を会得する。研究遂行、および論文作成のための基本的スキルを身につける。研究結果をまとめ修士論文を作成する。得られた成果を関連学会等で発表することが望ましい。 |
※共通科目は、全専攻で科目名は共通ですが、それぞれの研究テーマに沿って担当教員のもと研究を進めていく科目のため、具体的な内容は各人で異なります。
健康科学研究科 健康栄養学専攻(修士課程)
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 食材供給学特論 | 食と栄養の専門家として身に付けなければならない食料の生産と供給の実態を学ぶことを目的とする。わが国は食料の多くを海外に依存していることから、世界的に見た食料生産・供給の安定性や、生産現場から食卓までの食料供給行程の各段階における安全性確保の仕組み、関連の法制度などを学ぶとともに、食材汚染に起因する食品事故の発生メカニズムを解析する能力を養う。 |
| 栄養生化学特論 | 管理栄養士は、病院や施設における患者や利用者の栄養管理、事業所、学校、保育園等における栄養指導・教育に加え、栄養学の新しい知見を得るための研究活動も担っている。このための専門的知識を修得し、また、演習を通して実践力を養う。さらに、栄養生化学関連分野の研究論文(英文論文を含む)を調べ、理解し、発表する能力を身に付けることにより、実践の場でより高度な栄養指導を行うことができるようになり、また栄養学の最新の知見を正しく評価できるようになる。 |
| 食品機能学特論 | 近年、食生活や社会環境の変化に伴って様々な生活習慣病が増加している。この対策として、食品の体調調節機能への期待が高くなってきていることから、本授業では、食品及びその成分が人体の生理機能に及ぼす影響を理解する。さらに、関連する研究論文を探索、理解し発表する演習を通し、栄養マネジメントや研究に活用できる能力を身につける。 |
| 臨床栄養学特論 | 肥満症や生活習慣病などの予防と食事療法、食事療法が重要な役割を持つ疾患の診断・治療の理解、入院(所)患者の栄養管理、Nutrition support team(NST)での中核的役割などに関する専門的知識を修得する。また、演習を行うことにより、実践力を身に付ける。独自に関連分野の研究論文を調べ、理解し、発表する能力を培う。 |
| 栄養教育学特論 | 食育などの栄養教育の現場で、行動科学理論に基づいた栄養教育プログラムの開発や実践・評価法が研究されている。本特論では、栄養教育の行動科学理論や方法論、実践的な栄養教育プログラムに関する理解を深める。さらに、関連分野の研究論文を調べ、理解し、発表する能力を培う。 |
| 食生活学特論 | うつ病と栄養、リハビリテーションと調理実習、高齢者のフレイルと栄養・調理、災害時の栄養、ナトカリ比を活用した地域の高血圧予防の中から興味のある分野を選び、文献を調べ、理解し、発表する能力を身に付ける。 |
| 健康増進学特論 | 健康増進学の視点から、食品・栄養及び健康について、食生活全般を通して科学的に考察し、食生活の社会的背景、諸問題、及び今後の課題に至るまで展開し、理解を深める。健全な生活を営むための食生活のあり方について、生活習慣病の予防、Quality of life(QOL)の向上、及び健康寿命の延伸などの視点から考察し、議論する。健康の保持増進や生活の質の向上を目的として生活習慣病などの一次予防の視点を中心に、個人・集団・地域・栄養課題に対する、アセスメント・計画・実施・評価に関する研究を行う能力を養う。 |
健康科学研究科 博士課程 共通
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学特別研究 | 研究テーマの分野への理解を深め、指導教員の指導下で研究活動を行い、得られた研究成果に基づき、博士論文を作成する。また、3ポリシーを踏まえ、博士課程修了後に自らが有する学識を教授するために必要な能力を培う学修を行う。 |
※共通科目は、全分野で科目名は共通ですが、それぞれの研究テーマに沿って担当教員のもと研究を進めていく科目のため、具体的な内容は各人で異なります。
健康科学研究科 健康科学専攻 健康栄養学分野(博士課程)
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 食材供給学特講 | 食と栄養の専門家として身に付けなければならない食料の生産と供給の実態を学ぶことを目的とする。我が国は食料の多くを海外に依存していることから、世界的に見た食料生産・供給の安定性や、生産現場から食卓までの食料供給工程の各段階における安全性確保の仕組み、関連の法制度などを深く学ぶとともに、食材汚染に起因する食品事故の発生メカニズムを解析する高度な能力を養う。修士課程で修得した知識・技能をさらに深める。 |
| 栄養生化学特講 | 管理栄養士には病院や施設における非健常者への栄養管理、各種事業所での肥満や生活習慣病等の予防のための栄養指導、学校や保育所での栄養教育等、種々の重要な役割が課される。これに加えて栄養学の新しい知見を得るための研究活動をも担う。これらの基礎をなすのが栄養生化学の知識と経験である。このため授業をとおして知識を修得し、さらに栄養生化学関連分野の研究論文(英文論文を含む)を調べ、理解し、発表する演習を通して実践力を身に付ける。これらを修得することにより、職場でより高度な栄養指導を行ない、また栄養学の新知見を生み出す研究能力を身に付けられる。 |
| 食品機能学特講 | 近年、食生活や社会環境の変化に伴って増加している生活習慣病の対策として、食品の第三次機能(体調調節機能)への期待が高くなってきている。本特講では、食品及びその成分の第三次機能について理解する。さらに、食品及びその成分による疾病予防や健康保持の可能性に関する研究論文を探索、理解し発表する演習により実践力を培う。これらの修得を通して、栄養マネジメントや研究に活用できる、より高度な能力を身につける。 |
| 臨床栄養学特講 | 肥満症や生活習慣病などの予防と食事療法、食事療法が重要な役割を持つ疾患の診断・治療の理解、入院(所)患者の栄養管理、Nutrition support team(NST)での中核的役割などに関する高度な専門的知識を修得する。また、演習を行うことにより、実践力を身に付ける。独自に国内外の関連分野の研究論文を調べ、理解し、発表する能力を培う。 |
| 栄養教育学特講 | 食育などの栄養教育の現場で、行動科学理論に基づいた栄養教育プログラムの開発や実践・評価法が研究されている。本特論では、高度な栄養教育の行動科学理論や方法論、実践的な栄養教育プログラムに関する理解を深める。また、演習を行うことにより、実践力を身に付ける。さらに、国内外の関連分野の研究論文を調べ、理解し、発表する能力を培う。 |
| 食生活学特論 | メンタルヘルスと栄養、災害栄養、ナトカリ比を活用した地域の高血圧予防等についての理解を深める。国内外の文献を調べ、理解し、発表する力を培う。さらに、研究結果を現場に活かす方法を身につける。 |
| 健康増進学特論 | 健康増進学の視点から、食品・栄養及び健康について、食生活全般を通して科学的に考察し、食生活の社会的背景、諸問題、及び今後の課題に至るまで展開し、理解を深める。健全な生活を営むための食生活のあり方について、生活習慣病の予防、Quality of life(QOL)の向上、及び健康寿命の延伸などの視点から考察し、議論する。健康の保持増進や生活の質の向上を目的として生活習慣病などの一次予防の視点を中心に、個人・集団・地域・栄養課題に対する、アセスメント・計画・実施・評価に関する研究を行う能力を養う。さらには、国内外の関連分野の論文を調べ、考察し、議論する能力を身に付け、自分の研究課題の仮説検証及び研究成果を十分に考察する能力を習得する。 |
 対象者別
対象者別 検索
検索 入学者選抜情報
入学者選抜情報 学部/大学院
学部/大学院 キャンパスライフ
キャンパスライフ 交通アクセス
交通アクセス WEBオープンキャンパス
WEBオープンキャンパス 資料請求
資料請求 インターネット出願
インターネット出願 相談/学校見学
相談/学校見学