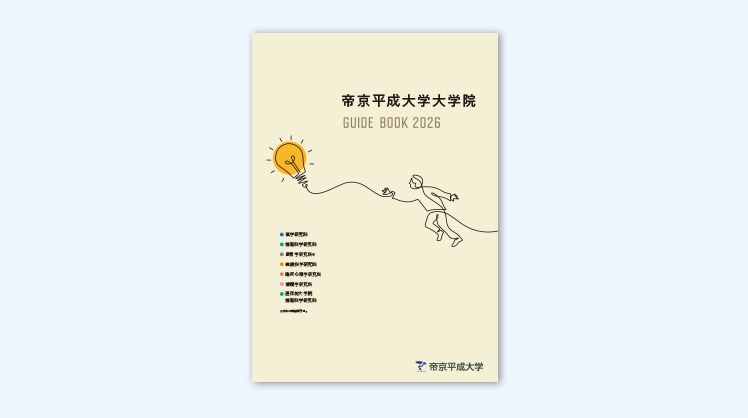健康科学研究科 鍼灸学専攻(修士課程)・健康科学研究科 健康科学専攻 鍼灸学分野(博士課程)


臨床現場を提供し、学術活動や鍼灸学への
造詣を深めることができます
健康科学研究科 鍼灸学専攻修士課程
国家資格を取得し、はり師・きゅう師として社会に出ても医療従事者としてはまだまだ駆け出しです。そこから一人前になるには何段階ものステップを踏む必要があります。また、学士課程や専門士課程での学業は鍼灸医学の基礎を学んで、はり師・きゅう師の国家試験に備える側面が強く、他人の研究成果を見聞して理解したり、自分のそれを発信したりする学術的な修練は不完全なまま終わっていると思われます。これらのニーズに対応するために鍼灸学専攻が設置されました。
本専攻は鍼灸学における第一線の研究成果を上げることを目標としています。そのために、まず「臨床鍼灸学特論I」「臨床鍼灸学特論II」「統合医療学特論I」「統合医療学特論II」「中医学特論」などの授業で学んだ鍼灸医学に関連する基礎知識を復習しつつ、さらに発展的な専門知識を身につけていきます。臨床実習では、帝京池袋鍼灸院・鍼灸臨床センターなどの臨床現場で実際に鍼灸治療を修練し、臨床家としてより高度なレベルを目指します。これらの経験を通じて鍼灸医学の抱えている問題点を自覚し、自分の研究テーマとすることも可能です。さらに、本専攻では国外での鍼灸事情に精通している教員から世界的な視野で鍼灸医学を学び、国際舞台で活躍できる素養を身につけることができます。
以上のように、本専攻では研究者としても臨床家としても独り立ちできるような実力を身につけるために必要な内容を学ぶ機会が与えられます。単に学位を取得するだけではなく、社会に出て力強く羽ばたいていきたいと考える方に最適と自負しております。
健康科学研究科 鍼灸学専攻(修士課程)のメリット
健康科学研究科 鍼灸学専攻(修士課程)では、「一般教育訓練給付金制度」の対象として、指定を受けています。
健康科学研究科 健康科学専攻鍼灸学分野(博士課程)
鍼灸学分野の目的は、修士課程までに修得した鍼灸学領域の知識をさらに発展させ、将来独創性の高い基礎研究を遂行できる研究者または高度な専門性を有した医療人となるための能力を培うことです。そのために様々な知見を修得する講義と演習からなる本専攻の専門科目に加え、鍼灸医学領域の研究者または医療人になるために必須となる「健康科学特別研究」によって構成されるカリキュラムが用意されています。
健康科学研究科 健康科学専攻(博士課程)のメリット
健康科学研究科 健康科学専攻(博士課程)では、「一般教育訓練給付金制度」の対象として、指定を受けています。
専攻長からのメッセージ
科学的な見識と技法を修得した将来の指導者を養成

本専攻では、基礎及び臨床研究を通して、鍼灸学における専門的な学識を深めます。ストレス社会と言われる近年、西洋医学のみでは対応が十分とは言えない疾患や症状が増え、様々な医療職種が連携した統合医療の必要性が求められています。特に、鍼灸治療は慢性疼痛やストレス症状の緩和、免疫機能の増大などに効果があり、統合医療の一翼として用いられています。今後、さらに現代社会における鍼灸治療の利用を広げることで、多くの人々の苦痛軽減に貢献できるはずです。そのためには、鍼灸の効果や機序を様々な視点から学際的に捉えることがより求められます。本学の実学の精神のもと、鍼灸学における科学的な見識・技法を修得し、研究と臨床の両面に優れた将来の指導者を養成します。
POINT はり師及びきゅう師養成施設における教員の資格が得られます
本専攻の修士課程を修了した場合、はり師・きゅう師養成施設における専門基礎分野及び専門分野に関する科目を教授するための教員資格が得られます。ただし、教授できる授業科目は、原則として専攻した分野に関連する領域となります。
特色
東洋医学研究所を中心とする研究施設で、鍼灸学の学問的造詣を深めます
本専攻には、鍼灸学やそのほかの東洋医学・伝統医学のスペシャリストがそろっております。主な研究施設である東洋医学研究所では、現在も共同研究をはじめ何件もの研究が彼らを中心に行われており、学会発表や論文発表も積極的に行っています。本専攻の学生も当研究所をベースに研究活動を行うことになり、場合によっては関連他施設の研究に関わる可能性もあります。学問的な物の考え方、研究の組み立て、文献検索、論文の作成など研究者としての基礎を学びます。
関連臨床施設で鍼灸の臨床に関する知識、技能を深めます
本専攻では、池袋キャンパス敷地内に帝京池袋鍼灸院・鍼灸臨床センターを附属臨床施設として使用しております。また池袋キャンパス敷地内には、このほかにも帝京池袋接骨院や帝京サンシャイン前接骨院、帝京平成大学臨床心理センターなどが併設されています。これらを通じて鍼灸の技術だけではなく、わが国の医療における鍼灸の果たす役割等も意識することができ、臨床面においても一段上のレベルを目指すことが可能です。
課程修了の認定及び学位
健康科学研究科 鍼灸学専攻(修士課程)
| 課程 | 修士 |
|---|---|
| 在学期間 | 2年以上4年以下 |
| 修得単位及び条件 |
|
| 学位 | 修士(健康科学) |
健康科学研究科 健康科学専攻 鍼灸学分野(博士課程)
| 課程 | 博士 |
|---|---|
| 在学期間 | 3年以上6年以下 |
| 修得単位及び条件 |
|
| 学位 | 博士(健康科学) |
教育研究及び担当教員
※担当教員、研究指導内容等は変更になる場合があります。
健康科学研究科 鍼灸学専攻(修士課程)
生化学、メタボロミクス
教授 和泉 孝志
鍼灸の生体に及ぼす作用とその機序について、物質代謝の側面から解析します。鍼灸刺激が物質代謝に及ぼす影響についての研究指導を行います。
神経免疫学、統合医療
教授 久島 達也
近年、腸内環境や消化管知覚情報が脳の機能に影響を与える根拠が報告され、腸が心の健康に影響を与えるという説に支持が集まっています。鍼灸刺激や生物学的応答調節物質(BRM)が脳と腸に及ぼす影響について神経免疫系の関係を中心とした研究の指導を行います。
神経科学(脳機能イメージング)、東洋医学(鍼灸)
教授 玉井 秀明
情動や認知機能に関わる前頭前野に対する鍼灸刺激の効果及びその作用機序の解明を目指し、脳機能イメージング法を用いた研究指導を行います。
社会医学、東洋医学(鍼灸)
教授 宮﨑 彰吾
社会問題の解決に向けた、鍼灸や触れること(体性感覚刺激)を活かした創意工夫及び臨床研究・疫学研究に関する指導を行います。
鍼灸科学、生理学、神経科学、疼痛制御
准教授 今井 賢治
鍼灸の生体に及ぼす作用とそのメカニズムについて評価・解析を行います。生理学及び神経科学的な実験技法を用いて、鍼灸刺激の末梢受容から中枢・末梢神経系を介した臓器・器官への作用を明らかにします。
東洋医学(鍼灸)
准教授 渡邉 大祐
東洋医学、特に鍼灸・経絡経穴に関する標準化を目標に、古今の文献を対象としたシステマティックレビューを含む手法を用いた文献研究の指導を行います。
東洋医学(鍼灸)
准教授 皆川 陽一
痛み(特に筋痛疾患)に対する鍼灸の治効機序及び疼痛症状における鍼灸の役割についての研究指導を行います。
鍼灸施術の安全管理、運動器障害と鍼灸施術
准教授 恒松 美香子
衛生管理を中心に安全な鍼灸施術の構築に向けて指導を行います。また、中高齢者を中心とした運動器障害に対する鍼灸施術の効果的な活用法に関しての研究指導を行います。
スポーツ医学(鍼灸、ロコモティブシンドローム)
講師 池宗 佐知子
ロコモティブシンドロームの予防や鍼灸治療の効果を解明することを目標として、静的・動的な評価方法を用いた研究の指導を行います。
人間医工学(東洋医学、睡眠学、人体美学)
講師 中村 優
東洋医学のシステムを工学的な手法で評価することを目標として、主に睡眠学と人体美学(美学、顔学、身体学、音声学など、『人』と『美』に関連する分野を総称しています)に着目して研究指導を行います。
東洋医学(鍼灸)、心身医学、予防医学、スポーツ医学
講師 脇 英彰
メンタルヘルスの維持・増進のために、精神、睡眠、認知の観点から心身に対する鍼灸治療の効果を解明することを目指して、基礎・臨床研究の指導を行います。
東洋医学(鍼灸)、運動生理学、免疫学
講師 小峰 昇一
東洋医学・西洋医学の異なる研究分野を融合した新たな領域を構築し、この融合研究の有効性を実証することを目指します。その1つとして、生理学・生化学解析を用いて、鍼治療が骨格筋や免疫応答に与える効果に着目した基礎・臨床研究の指導を行います。
健康科学研究科 健康科学専攻 鍼灸学分野(博士課程)
生化学
教授 医学博士 和泉 孝志
鍼灸の生体に及ぼす作用とその機序について、物質代謝の側面から解析します。鍼灸刺激が物質代謝に及ぼす影響についての研究指導を行います。
社会鍼灸学
教授 博士(医学) 宮﨑 彰吾
社会問題の解決に向けた、鍼灸や触れること(体性感覚刺激)を活かした創意工夫及び臨床研究・疫学研究に関する指導を行います。
神経免疫学
教授 博士(医学) 久島 達也
神経免疫関連疾患に対する有効な予防及び治療法の確立を研究の目標として、鍼灸や生物反応修飾物質(BRM)などの刺激が神経系や免疫系機能に及ぼす影響について研究の指導を行います。〈研究課題〉自律神経系と免疫系機能に対する鍼灸刺激の作用機序の解明粘膜免疫機能に及ぼすBMRの有効性に関する臨床研究など。
基礎鍼灸医学(環境生理学)
教授 博士(医学) 久島 達也
ヒトに対する鍼や灸などの体性感覚刺激が様々なストレス環境にある生体に及ぼす影響について自律神経機能などの客観的な評価により検証し、その結果を博士論文として作成できるよう個別的に指導を行います。
神経科学
教授 博士(医学) 久島 達也
鍼灸刺激による脳機能障害の改善法の確立を目標とし、神経科学分野において自ら独創的な課題を発想し研究活動を遂行していくために必要となる知識及び思考能力を養い、近年、広く利用されている脳機能計測等の技術を研究に応用できる人材への成長を促進する指導を行います。
神経科学
教授 博士(医学) 玉井 秀明
情動や認知機能に関わる前頭前野に対する鍼灸刺激の効果及びその作用機序の解明を目指し、脳機能イメージング法を用いた研究指導を行います。
鍼灸科学
准教授 博士(鍼灸学) 今井 賢治
鍼灸の生体に及ぼす作用とそのメカニズムについて評価・解析を行います。生理学及び神経科学的な実験技法を用いて、鍼灸刺激の末梢受容から中枢・末梢神経系を介した臓器・器官への作用を明らかにします。
東洋医学(鍼灸)
准教授 博士(鍼灸学) 皆川 陽一
痛み(特に筋痛疾患)に対する鍼灸の治効機序及び疼痛症状における鍼灸の役割についての研究指導を行います。
東洋医学(鍼灸)
准教授 博士(医学) 渡邉 大祐
東洋医学、特に鍼灸・経絡経穴に関する標準化を目標に、古今の文献を対象としたシステマティックレビューを含む手法を用いた文献研究の指導を行います。
授業科目の概要
※授業科目等は変更になる場合があります。
健康科学研究科 修士課程 全専攻共通
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学研究法特論Ⅰ | 健康科学分野、特に臨床における研究の意義と研究論文作成の一連のプロセスを理解し、高度専門職としての実践に貢献する研究方法論を学修することで、専門演習や特別研究を実施するための基礎を作る。具体的には、保健や医療領域における具体的研究例を学ぶことを通して、研究計画の立案、データ収集と分析、研究成果のまとめ方に関する知識・技術を養う。 |
| 健康科学研究法特論Ⅱ | 院生各自の具体的な研究方法は「健康科学特別研究」で研究指導教員から学ぶことになっている。しかし、異なる研究分野における研究手法など、自分の研究では学修できないような研究内容を知ることも必要である。このような観点から、本科目は「健康科学研究法特論Ⅰ」に続く共通科目として設定し、健康科学分野の研究方法と研究論⽂作成のプロセスをより深く理解し、習熟することを到達目標とする。具体的な研究例を学ぶことを通して、研究計画の⽴案、データ収集と分析、研究成果のまとめ⽅、およびプレゼンテーションに関する知識とスキルを身に付ける。 |
| 医療統計学特論 | 科学的根拠に基づく医療(Evidence-Based Medicine:EBM)を実現させるために様々な研究が行われており、その結果を判断する上で統計学はとても重要な役割を果たしている。そのため研究デザインの段階で得られるデータの性質や解析手法をきちんと考え決めておく必要がある。本講義では、統計学におけるデータ解析の基礎的な内容から始まり、主要な統計手法について講義を行い、修士・博士課程での研究における統計処理をSPSSを用いて実践する内容とする。 |
| 医療教育学特論 | 保健医療専門職として、後進育成のために必要な教育学に関する基礎的知識と教育方法を学ぶことが目的である。また、現在の保健医療福祉領域で課題となる多重問題ケースに対応するために多職種連携教育・協働について学び、リーダーシップを担うべく知識と技術の基盤を修得することも目的とする。 |
| 保健医療管理学特論 | 保健や医療サービスシステムの現状を把握するとともに保健医療に携わる医療関連職種が直面している課題について討議し、サービスシステムを説明し課題を明らかにすることができるようにする。患者ケアシステムを実行する上で不可欠なマネージメントを学び、専門的知識・技術を有効に活用できる能力を養う。他職種の医療サービスシステムを学ぶことで他職種連携についての理解を深め、多職種協働の実践に役立てる。 |
| 健康医科学特論 | 臨床現場で関わる傷病・疾患は各医療専門職により異なる。しかし、罹患率の高い生活習慣病などに関する知識は、すべての医療専門職に必要である。疾病予防や健康維持の観点からは、成長期や青年期の健康医学の理解も重要である。臨床医学分野の最新の知識を学ぶことは、自らの生涯学習として有用なだけでなく、専門職として接する患者や家族の状況を理解し、専門的判断を構築する際に役立つと思われる。 到達目標:臨床医学一般についての知識を広げ、深めることを目標とする。 |
| 医科学英語特論 | 科学的研究分野で使われる英語や医療英語は、一般的英語と異なる点がある。英会話を含め一般的英語が得意な人でも、医療や研究分野の専門英語に慣れる必要がある。専門職業人や教育者、特に研究者をめざす大学院修士課程の院生にとって、専門分野の英語文の読解や作成能力は将来必要な基礎学力である。 到達目標:この授業では、健康科学や医学医療分野の英文読解力を向上させることを主目標とする。 |
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学特別研究 | 指導教員の指導下で修士研究を行い修士論文を作成する研究科目である。2年間の概略は次の通りである。 【1年目】実施予定の研究に関する情報集積を行い、研究の目的と方法を明確にし、研究計画を作成する。研究倫理を理解し、研究倫理教育のコースを修了する。倫理審査の承認後、研究を開始する。 【2年目】研究計画に基づいて研究を遂行し、修士論文を完成させる。研究が計画に沿って進んでいることを確認し、研究結果を分析し考察を行う。研究テーマや研究方法の変更が必要になった場合は、速やかに研究計画を修正する。倫理審査申請書類の再提出など必要な手続きを行う。 到達目標:研究倫理を理解し、倫理審査申請書類の作成を会得する。研究遂行、および論文作成のための基本的スキルを身につける。研究結果をまとめ修士論文を作成する。得られた成果を関連学会等で発表することが望ましい。 |
※共通科目は、全専攻で科目名は共通ですが、それぞれの研究テーマに沿って担当教員のもと研究を進めていく科目のため、具体的な内容は各人で異なります。
健康科学研究科 鍼灸学専攻(修士課程)
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 基礎鍼灸学特論 | 本講義の目的は、高度で専門的な鍼灸臨床に必須となる鍼灸の治効理論を修得することである。ここでは、鍼灸刺激が生体に対してどのような機序で影響を及ぼすかについて情報伝達や生体反応を含んだ鍼灸治効の基礎、自律神経や生体防御機構における一般治効理論及び鍼灸の臨床評価について理解を深める。加えて、臨床鍼灸学特論Ⅰ及び臨床鍼灸学特論Ⅱの理解に役立てる。 |
| 臨床鍼灸学特論Ⅰ | 臨床鍼灸学特論Ⅰでは、将来の高度で専門的な鍼灸臨床に必要な最近の知見も含めた治効理論を実践的に理解する。ここでは、生体に対する鍼灸刺激により得られる自律神経、生体防御機構などの情報を測定し、その結果を基礎鍼灸学特論で修得した一般治効理論により評価する。これにより実務で求められる客観的なインフォームドコンセント能力を向上させる。 |
| 臨床鍼灸学特論Ⅱ | 臨床鍼灸学特論Ⅱでは、様々な疾患や症候に対して科学的根拠にもとづいた鍼灸治療の診断法、治療法について学修する。実際の病態から得られる情報を評価し、基礎鍼灸学特論、臨床鍼灸学特論Ⅰで修得した治効理論を用いて解釈することで、鍼灸治療の診断治療学を客観的に理解する。また、これにより、学際的な成果を自ら報告できる人材を育成する。 |
| 中医学特論 | 中医学は「整体観念」と「弁証論治」を特徴として、独自の理論体系を確立している。本講義は、中医学理論の基盤となる古典について、理解を深めることを目的とする。具体的には、中医学理論の背景にある思想とともに、形態観・機能観、病因病機、診察法、診断法、治療法に関する古典の要点とその臨床応用について学ぶ。さらに、日本伝統鍼灸との共通点と相違点も把握することで、中医学への理解の向上につなげる。 |
| 疼痛制御学特論 | 痛みによる生体反応と、鍼灸刺激による鎮痛作用のメカニズムを学ぶ。関連する疼痛制御系として、末梢性鎮痛、下行性抑制系、広範性侵害抑制、脊髄後角における鎮痛系などを理解し、臨床に応用することを学ぶ。 |
| 統合医療学特論Ⅰ | 統合医療の基礎的知識としてのCAMやEBMを調査した後、統合医療の現状や教育システムの実際と課題、医療行政との関係、東洋の各種伝統医療について、フィールドも含め研修する。その後、EBMの確立に向けた研究の基礎的調査法について学ぶ。 |
| 統合医療学特論Ⅱ | 統合医療の先端医学的アプローチによるEBMを目指した研究を実践する。特に鍼灸などに関して、緩和ケア病棟や高齢者福祉関係施設において、最先端医療機器を駆使してEBMを確立する研究や、鍼灸などの応用による生理・心理・生化学的変化についてのヒト試験を行い、英語の論文あるいは報告書として発表する。 |
| 附属治療院特別演習 | 附属治療院での診察から治療、及びそれらの評価に至る臨床鍼灸の流れを学び臨床力を高める。経験した症例は、病態把握や治療方法などを再検討し、その問題点を整理することで自身での問題解決能力を向上させる。また、カンファレンスにてその考えや問題点を教員や他の学生に発表し、自分の意見を他人に伝え、議論できる能力を身に付ける。 |
健康科学研究科 博士課程 共通
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学特別研究 | 研究テーマの分野への理解を深め、指導教員の指導下で研究活動を行い、得られた研究成果に基づき、博士論文を作成する。また、3ポリシーを踏まえ、博士課程修了後に自らが有する学識を教授するために必要な能力を培う学修を行う。 |
※共通科目は、全分野で科目名は共通ですが、それぞれの研究テーマに沿って担当教員のもと研究を進めていく科目のため、具体的な内容は各人で異なります。
健康科学研究科 健康科学専攻 鍼灸学分野(博士課程)
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 鍼灸学特講 | 本講義では、これまでに習得した鍼灸学領域の知識をさらに発展させ、将来独創性の高い基礎研究を遂行できる研究者の育成を目的とする。鍼灸刺激が神経系や免疫系など生体調節機能に対して作用する際の機序について、鍼灸治効理論の先端的知見に焦点をあて理解を深める。 |
| 統合医療学特講 | 統合医療の臨床的有効性のメカニズムの解明を目指すべく、臨床疫学的研究から試験管内実験、特に病態動物を使った病理学的研究や遺伝子を対象にした試験管内実験などの幅広いアプローチの必要性を紹介する。その過程で、基礎から臨床医学までの研究手技から解析・評価手法に親しむ。具体事例として、糖化と血管内皮細胞機能が、未病発症や経絡概念において果たす役割を明らかにすることで、東西医学が統合できる可能性を紹介する。 |
| 鍼灸臨床演習 | 本演習では、患者の病態を的確に判断した上でエビデンスに基づく鍼灸治療方針を立案できる臨床知識を修得する。さらに、患者からインフォームドコンセントを取得し、安全な鍼灸治療を行い、患者の信頼を得るという一連のプロセスを遂行できる臨床力の育成を目的とする。また、診療情報をもとに他の医療機関と連携した鍼灸臨床を行える能力を養う。 |
| 中医学特講 | 中医学は「整体観念」と「弁証論治」を特徴として、独特の理論体系を確立している。本講義は、中医学の古典、現代の中医学、中医学を応用した現代医学的研究論文等の精読と討論を通じて、中医学の背景にある哲学から現代までの発展について理解を深める。 |
| 疼痛医学特講 | 本講義では、国内外の痛みに関する情報を基に、「疼痛医学」を取り巻く状況について理解し、根拠に基づいた情報を提供できる知識を養う。 |
 対象者別
対象者別 検索
検索 入学者選抜情報
入学者選抜情報 学部/大学院
学部/大学院 キャンパスライフ
キャンパスライフ 交通アクセス
交通アクセス WEBオープンキャンパス
WEBオープンキャンパス 資料請求
資料請求 インターネット出願
インターネット出願 相談/学校見学
相談/学校見学