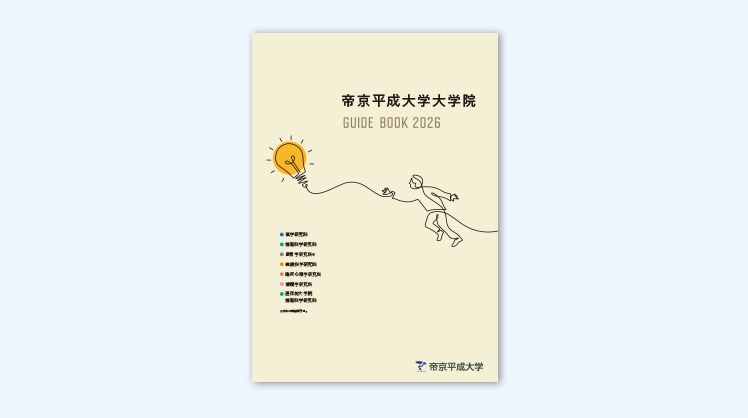健康科学研究科 病院前救急医療学専攻(修士課程)・健康科学専攻 病院前救急医療学分野(博士課程)


病院前救急医療学の基礎を築き、
新たな時代を創る指導的な人材を養成します
健康科学研究科 病院前救急医療学専攻修士課程
救急救命士制度の誕生から30年以上が経過した昨今、高齢化による重症傷病者の搬送件数が増加し、医学的処置を行いながら搬送する救急救命士が注目されています。これまで救急救命士の働く職場は消防機関に限定されておりましたが、2021年の救急救命士法の改正により、病院内でも救急救命処置が行えるようになりました。近年、救急救命士による処置範囲拡大の議論が進む中、医学的知識や技術を深めた救急救命士が救急搬送に関わるようになり、病院前救急医療に関心が集まっています。
病院で行われている医療とは大きく異なる病院前救急医療では、学問体系が未だ確立されていない現状にあります。このような状況にあって本専攻では、日本救急医学会の救急専門医として救急医療の最前線である救命救急センターなどで活躍してきた教授陣を中心に、病院前救急医療学の基礎を築き、新たな時代を創る指導的人材の養成を目指しています。
具体的には、蘇生学、外傷学、災害医学、急性中毒学、救急医療システム学などについて専門の教員から指導を受けます。救急医療システム学については、日本の現状を知るばかりではなく、欧米のシステムの現状を学んで今後のわが国のシステム改善に向けた議論を深めることを目標にしています。また、東日本大震災後に注目されている災害医学についても「救急救命士に何ができるのか」を問い直すことから検討しているところです。
ハードルはまだまだ高いものの、救急救命士の活躍の場は今後さらに拡大するものと期待されます。そのときにすぐ役に立つ人材を育てていくのが本専攻の責務と考えています。
健康科学研究科 病院前救急医療学専攻(修士課程)のメリット
健康科学研究科 病院前救急医療学専攻(修士課程)では、「一般教育訓練給付金制度」の対象として、指定を受けています。
健康科学研究科 健康科学専攻病院前救急医療学分野(博士課程)
病院前救急医療は、国民の生活に直結する重要な社会インフラです。救急搬送サービスに医療の視点を取り込んだ救急救命士制度において指導者としての資質を有する人材が求められています。博士課程では、病院前救急医療学の知識を蓄積し、拡大・精選・伝達し得る能力を養い、自立して病院前救急医療学の研究・開発ができる専門家を養成することを目的としています。
健康科学研究科 健康科学専攻(博士課程)のメリット
健康科学研究科 健康科学専攻(博士課程)では、「一般教育訓練給付金制度」の対象として、指定を受けています。
専攻長からのメッセージ
国際的な視野を持ち、後輩救急救命士を教育・指導できる人材を養成します

本専攻は、指導的な救急救命士を養成するために生まれた専攻です。救急救命士が誕生して30年以上が経過した今日、専門職として先輩救急救命士が自分たちの後輩を育てていく時代が来たと思われます。そのためには国際的な視野を持ち、科学的思考力を身につけて、高等教育機関で教育職に就く学識と能力を持った指導的な救急救命士が求められます。病院前救急医療に関わる幅広い領域に問題点を見つけ、科学的な思考で解決していく能力を身につけた人材を養成します。
特色
充実した教授陣により指導的救急救命士を養成します
本専攻では、救命救急センターで長年経験を積んだ日本救急医学会専門医等が教授陣として救急救命士の指導者となるべき人材の養成に努めています。病院前救急医療には医療の視点を持った指導的救急救命士の存在が求められています。そのため、関連する救命救急センターで研修を行うなど、医療の現場との接点を大切にするとともに、国際的視野を持った研究者として、また優れた指導者として自立できるよう指導しています。
多様な医療関連の学問を学び、多彩な医療職とコミュニケーションを取れる能力を身につけます
今、医療界ではチーム医療が大切なキーワードになっています。医療に関わる多くの職種の人たちがコミュニケーションを通じて関わり合い、医療の質の向上を目指しています。健康科学研究科は、本専攻を含む9つもの医療に関する専攻があります。院生同士あるいは院生と教員の交流により、多様な医療関連の学問に接するとともに、他職種とのコミュニケーションを通して医療人としての幅広い人間性を育むことができます。
課程修了の認定及び学位
健康科学研究科 病院前救急医療学専攻(修士課程)
| 課程 | 修士 |
|---|---|
| 在学期間 | 2年以上4年以下 |
| 修得単位及び条件 |
|
| 学位 | 修士(健康科学) |
健康科学研究科 健康科学専攻 病院前救急医療学分野(博士課程)
| 課程 | 博士 |
|---|---|
| 在学期間 | 3年以上6年以下 |
| 修得単位及び条件 |
|
| 学位 | 博士(健康科学) |
教育研究及び担当教員
※担当教員、研究指導内容等は変更になる場合があります。
健康科学研究科 病院前救急医療学専攻(修士課程)
病院前救急医療システム学
教授 藤田 尚
病院前救急医療の発展の経緯、救急救命士制度の現状と問題点について研究指導を行います。
外傷・感染と生体侵襲
教授 斧 康雄
教授 藤田 尚
外傷・感染の疫学、外傷・感染の病態、外傷・感染に対する生体反応などについて研究指導を行います。
急性中毒学
教授 阪本 奈美子
病院前救急医療に必要な急性中毒について研究指導を行います。
レーザー医療応用
教授 大森 繁
治療に用いるレーザー装置について、治療メカニズムと効果および安全性について研究指導を行います。
解剖学
教授 濱田 剛
救急隊員に求められる解剖学的知見について研究指導を行います。
臨床法医学
教授 阪本 奈美子
病院前医療における法医学的事項について学び、調査研究の計画、立案、実行について指導します。
災害医学
教授 矢島 務
准教授 染谷 泰子
災害時における病院前救急医療に関する研究指導を行います。
免疫・アレルギー学
教授 斧 康雄
教授 永川 茂
免疫・アレルギーの病態と対応について学び、研究指導を行います。
細胞組織学
教授 萩原 治夫
細胞内小器官、細胞骨格における機能分子局在について、研究指導を行います。
健康科学研究科 健康科学専攻 病院前救急医療学分野(博士課程)
病院前救急医療システム学
教授 博士(医学) 藤田 尚
我が国と諸外国の救急医療システムの違いを英語の文献で学び、救急救命士制度の現状と課題、指導者教育のあり方などについての研究指導を行います。
外傷・感染と生体侵襲
教授 博士(医学) 斧 康雄
教授 博士(医学) 藤田 尚
外傷・感染の病態、外傷傷病者の病院前救護などについて最新の文献を基に深く学ぶとともに研究指導を行います。
急性中毒学
教授 博士(医学) 阪本 奈美子
病院前救急医療に必要な急性中毒の病態や対応について学ぶとともに研究指導を行います。
臨床法医学
教授 博士(医学) 阪本 奈美子
病院前医療における法医学的事項につき調査・研究を行います。
- 外傷形態と死亡原因
- 死亡原因と死後画像
- 死後造影CTと心肺蘇生法など
免疫・アレルギー学
教授 博士(医学) 斧 康雄
教授 博士(医学) 永川 茂
病院前救急医療に必要な免疫・アレルギーの病態と対応について学び、研究指導を行います。
細胞組織学
教授 博士(医学) 萩原 治夫
細胞内小器官、細胞骨格における機能分子局在について、最新の知見を基に研究指導を行います。
授業科目の概要
※授業科目等は変更になる場合があります。
健康科学研究科 修士課程 全専攻共通
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学研究法特論Ⅰ | 健康科学分野、特に臨床における研究の意義と研究論文作成の一連のプロセスを理解し、高度専門職としての実践に貢献する研究方法論を学修することで、専門演習や特別研究を実施するための基礎を作る。具体的には、保健や医療領域における具体的研究例を学ぶことを通して、研究計画の立案、データ収集と分析、研究成果のまとめ方に関する知識・技術を養う。 |
| 健康科学研究法特論Ⅱ | 院生各自の具体的な研究方法は「健康科学特別研究」で研究指導教員から学ぶことになっている。しかし、異なる研究分野における研究手法など、自分の研究では学修できないような研究内容を知ることも必要である。このような観点から、本科目は「健康科学研究法特論Ⅰ」に続く共通科目として設定し、健康科学分野の研究方法と研究論⽂作成のプロセスをより深く理解し、習熟することを到達目標とする。具体的な研究例を学ぶことを通して、研究計画の⽴案、データ収集と分析、研究成果のまとめ⽅、およびプレゼンテーションに関する知識とスキルを身に付ける。 |
| 医療統計学特論 | 科学的根拠に基づく医療(Evidence-Based Medicine:EBM)を実現させるために様々な研究が行われており、その結果を判断する上で統計学はとても重要な役割を果たしている。そのため研究デザインの段階で得られるデータの性質や解析手法をきちんと考え決めておく必要がある。本講義では、統計学におけるデータ解析の基礎的な内容から始まり、主要な統計手法について講義を行い、修士・博士課程での研究における統計処理をSPSSを用いて実践する内容とする。 |
| 医療教育学特論 | 保健医療専門職として、後進育成のために必要な教育学に関する基礎的知識と教育方法を学ぶことが目的である。また、現在の保健医療福祉領域で課題となる多重問題ケースに対応するために多職種連携教育・協働について学び、リーダーシップを担うべく知識と技術の基盤を修得することも目的とする。 |
| 保健医療管理学特論 | 保健や医療サービスシステムの現状を把握するとともに保健医療に携わる医療関連職種が直面している課題について討議し、サービスシステムを説明し課題を明らかにすることができるようにする。患者ケアシステムを実行する上で不可欠なマネージメントを学び、専門的知識・技術を有効に活用できる能力を養う。他職種の医療サービスシステムを学ぶことで他職種連携についての理解を深め、多職種協働の実践に役立てる。 |
| 健康医科学特論 | 臨床現場で関わる傷病・疾患は各医療専門職により異なる。しかし、罹患率の高い生活習慣病などに関する知識は、すべての医療専門職に必要である。疾病予防や健康維持の観点からは、成長期や青年期の健康医学の理解も重要である。臨床医学分野の最新の知識を学ぶことは、自らの生涯学習として有用なだけでなく、専門職として接する患者や家族の状況を理解し、専門的判断を構築する際に役立つと思われる。 到達目標:臨床医学一般についての知識を広げ、深めることを目標とする。 |
| 医科学英語特論 | 科学的研究分野で使われる英語や医療英語は、一般的英語と異なる点がある。英会話を含め一般的英語が得意な人でも、医療や研究分野の専門英語に慣れる必要がある。専門職業人や教育者、特に研究者をめざす大学院修士課程の院生にとって、専門分野の英語文の読解や作成能力は将来必要な基礎学力である。 到達目標:この授業では、健康科学や医学医療分野の英文読解力を向上させることを主目標とする。 |
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学特別研究 | 指導教員の指導下で修士研究を行い修士論文を作成する研究科目である。2年間の概略は次の通りである。 【1年目】実施予定の研究に関する情報集積を行い、研究の目的と方法を明確にし、研究計画を作成する。研究倫理を理解し、研究倫理教育のコースを修了する。倫理審査の承認後、研究を開始する。 【2年目】研究計画に基づいて研究を遂行し、修士論文を完成させる。研究が計画に沿って進んでいることを確認し、研究結果を分析し考察を行う。研究テーマや研究方法の変更が必要になった場合は、速やかに研究計画を修正する。倫理審査申請書類の再提出など必要な手続きを行う。 到達目標:研究倫理を理解し、倫理審査申請書類の作成を会得する。研究遂行、および論文作成のための基本的スキルを身につける。研究結果をまとめ修士論文を作成する。得られた成果を関連学会等で発表することが望ましい。 |
※共通科目は、全専攻で科目名は共通ですが、それぞれの研究テーマに沿って担当教員のもと研究を進めていく科目のため、具体的な内容は各人で異なります。
健康科学研究科 病院前救急医療学専攻(修士課程)
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 病院前救急医療学特論 | 地域の救急医療において病院前救護(プレホスピタルケア)の重要性が高まりつつある。病院前救護の現状を分析し、問題点と改善の方策について議論し、理解を深める。特に救急救命士の指導者としての使命を理解してもらうように努める。 |
| 蘇生学特論 | 重症外傷や救急疾患にもとづく心肺停止やショックは、医学研究者にとって極めて重要な研究分野である。蘇生法については世界的なガイドラインが策定されているが、さらに効果的な蘇生方法を模索するために蘇生救護訓練を通じて蘇生方法の有効性の比較を中心に研究を行う。同時に、同じテーマに関する内外から発信される研究論文の抄読を通して論文作成の具体的指導を行う。 |
| 外傷学特論 | 外傷・感染傷病者に対する適切な対応は、救急医療の重要な課題の一つである。重症外傷・感染の疫学や病態の理解を深め、病院前救護から病院内での治療へと連携していくための知識や技能の修得には常に新しい知識の吸収が必要である。欧米から発信される最新の外傷・感染診療事情を学ぶために、英文臨床雑誌の抄読を行う。また、広く生体侵襲学の視点から修士論文作成に直結する様々な知識を学ぶ。 |
| 災害医学特論 | 自然災害、集団災害の実際を学び、医療関係者として災害現場で適切な行動がとれるように、限られた医療資源で最大限の命を救うという災害医療の目的を理解する。 |
健康科学研究科 博士課程 共通
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学特別研究 | 研究テーマの分野への理解を深め、指導教員の指導下で研究活動を行い、得られた研究成果に基づき、博士論文を作成する。また、3ポリシーを踏まえ、博士課程修了後に自らが有する学識を教授するために必要な能力を培う学修を行う。 |
※共通科目は、全分野で科目名は共通ですが、それぞれの研究テーマに沿って担当教員のもと研究を進めていく科目のため、具体的な内容は各人で異なります。
健康科学研究科 健康科学専攻 病院前救急医療学分野(博士課程)
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 病院前救急医療学特講 | 地域の救急医療において病院前救護(プレホスピタルケア)の重要性が高まりつつあり、救急救命士の指導者となり得る人材が求められている。病院前救護の現状と課題を分析し、病院前救護における学問体系を構築するための議論を通じて、救急救命士の指導者としての使命と役割を理解する。 |
| 蘇生学特講 | 重症外傷や救急疾患に基づく心肺停止やショックは、医学研究者のみならず病院前救護の担い手である救急救命士にとって、極めて重要な研究分野である。生命危機の迫った傷病者を想定した救護訓練による蘇生方法の効果比較と施行者自身が晒されるストレス反応を中心に研究を行う。同時に、内外から発信される研究論文の抄読を通して論文作成の具体的指導を行う。 |
| 外傷学特講 | 外傷・感染傷病者に対する適切な対応は、救急医療の重要な課題の一つである。重症外傷・感染の疫学や病態の理解を深め、病院前救護から病院内での治療へと連携していくための知識や技能の習得には常に新しい知識の吸収が必要である。欧米から発信される最新の外傷・感染診療事情を学ぶために、英文臨床雑誌の抄読を行う。また、広く生体侵襲学の視点から博士論文作成に直結する様々な知識を学ぶ。 |
| 災害医学特講 | 災害現場においては、医療関係者の一員として医師、看護師、薬剤師などのほか警察官、自衛隊員、行政職員、などと適切な情報交換を行うことが大切である。救急救命士が災害現場で適切な働きができるよう災害医学について理解を深め、あわせて災害医療における種々の問題点について考察する能力を身に付ける。 |
 対象者別
対象者別 検索
検索 入学者選抜情報
入学者選抜情報 学部/大学院
学部/大学院 キャンパスライフ
キャンパスライフ 交通アクセス
交通アクセス WEBオープンキャンパス
WEBオープンキャンパス 資料請求
資料請求 インターネット出願
インターネット出願 相談/学校見学
相談/学校見学