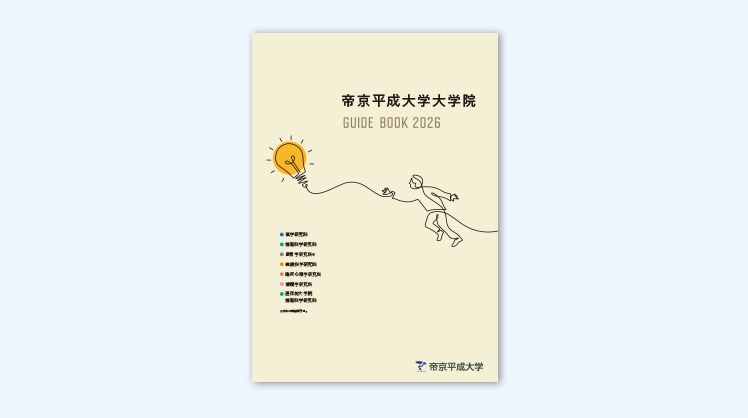健康科学研究科 言語聴覚学専攻(修士課程)・健康科学専攻 言語聴覚学分野(博士課程)


言語聴覚学領域における
指導的役割を担う臨床家、研究者を養成します
健康科学研究科 言語聴覚学専攻修士課程
- 言語聴覚学は、広い基礎知識を基盤とする学際的な応用の学問です
言語聴覚学は、正常なコミュニケーション過程の科学的究明を基盤として、言語・コミュニケーションの多種多様な問題に関して、その症状の記述、評価、原因の究明を目指す、いわば基礎と臨床を統合した学問分野です。言語科学系、心理・教育・社会科学系、医学系、工学系などに及ぶ広い基礎知識を基盤とする学際的専門領域であり、これらの基礎科学で得られた知識を応用して障害の治療に当たることを目的とします。
- 高度の専門性を持ち指導的役割を担う臨床家、研究者を養成します
近年、社会の高齢化、医療技術の進歩・高度化に伴う疾病構造の変化や社会システムの変化などに伴い、言語聴覚療法のニーズが多様化しています。本専攻では、これらの社会状況を踏まえ、人間のコミュニケーションの発達とその障害に対する豊かな知識を備え、多様な社会的ニーズに即した支援を行う高度の専門性を持ち、言語聴覚学領域における指導的役割を担う臨床家、研究者の養成を目指します。
- 言語聴覚学専攻で学ぶことは(専門科目について)
開講されている専門領域科目「言語聴覚学演習」では言語・コミュニケーションを生涯発達の視点から学びます。「言語聴覚障害学演習」では言語の諸問題を多面的・分析的に評価する方法論について、「言語聴覚療法学演習」では訓練技法や包括的支援について、これまでの研究の歩みを学びつつ、内外の文献講読や症例検討から最新の知見について学びます。
健康科学研究科 言語聴覚学専攻(修士課程)のメリット
健康科学研究科 言語聴覚学専攻(修士課程)では、「一般教育訓練給付金制度」の対象として、指定を受けています。
健康科学研究科 健康科学専攻言語聴覚学分野(博士課程)
言語聴覚学分野では、修士課程での教育研究をさらに深化させ、広く社会に貢献できる問題解決能力を持ち、言語聴覚領域の先駆的な研究を推進できる研究者、教育者、臨床家の養成を目指します。広い研究視野の形成のために、言語・コミュニケーションを生涯発達の視点から研究する「言語聴覚学」、言語の諸問題を多面的・分析的に評価するための方法論を研究する「言語聴覚障害学」、訓練技法や包括的支援について研究する「言語聴覚療法学」を教育の大きな3つの柱としています。
健康科学研究科 健康科学専攻(博士課程)のメリット
健康科学研究科 健康科学専攻(博士課程)では、「一般教育訓練給付金制度」の対象として、指定を受けています。
専攻長からのメッセージ
言語聴覚障害児・者が抱える多様な支援ニーズに応えるための専門的学修と研究指導

本専攻では、「言語聴覚学」「言語聴覚障害学」「言語聴覚療法学」の3つの研究分野について、学修と研究を行います。「言語聴覚学」は、主にコミュニケーションと言語の発達およびその障害について、生涯発達の視点から学び、言語聴覚障害研究の基礎能力を養います。「言語聴覚障害学」は、言語聴覚障害の各専門分野の諸問題を多面的視点から評価・分析するための最新の知識と研究方法を学修し、対象者の抱える問題を、包括的に解釈する力を養います。「言語聴覚療法学」は、各専門分野の訓練技法や包括的支援の方法論を研究し、臨床での実践能力の向上を目指します。本専攻では、各分野で豊富な臨床歴、研究歴を持つ教員が研究指導を行う体制が整っています。自らの明確な問いを持ち、粘り強く積極的に学修と研究を遂行できる人材を求めます。
特色
生涯発達の視点から、言語・コミュニケーション機能に関する基礎研究を進めます
乳幼児期から老年期に至る言語・コミュニケーションの発達とその基礎となる認知機能、聴覚、発声・発語機能の発達、およびそれぞれの発達段階で出現する問題や障害、加齢変化について、生涯発達の視点から総合的に学び、言語聴覚障害研究の基礎能力をつけます。言語・コミュニケーションについて各発達段階の特徴を考察しながら、神経心理学的視点、言語発達心理学的視点、認知心理学的視点などから研究を深めます。
多面的視点から評価・分析するための方法論、及び訓練・支援法の研究を進めます
観察法、調査法、実験法、事例研究法、エピソード記述を通した研究法など、言語・コミュニケーション障害の諸問題を評価・分析するための様々な方法論や、個人を包括的に捉える方法論を研究します。また、言語・コミュニケーション障害に対する機能訓練法、障害特性に応じたAACの適用などについて研究を深めます。生活支援、家族支援、教育支援、就労支援の視点から、臨床実践のあり方や地域社会への支援方法についても実証的な研究を行います。
課程修了の認定及び学位
健康科学研究科 言語聴覚学専攻(修士課程)
| 課程 | 修士 |
|---|---|
| 在学期間 | 2年以上4年以下 |
| 修得単位及び条件 |
|
| 学位 | 修士(健康科学) |
健康科学研究科 健康科学専攻 言語聴覚学分野(博士課程)
| 課程 | 博士 |
|---|---|
| 在学期間 | 3年以上6年以下 |
| 修得単位及び条件 |
|
| 学位 | 博士(健康科学) |
教育研究及び担当教員
※担当教員、研究指導内容等は変更になる場合があります。
健康科学研究科 言語聴覚学専攻(修士課程)
聴覚障がい児・者および盲ろう児・者のコミュニケーションとQOL、臨床発達支援に関連する分野
教授 黒田 生子
聴覚障害者(あるいは盲ろう者)のwell-being(健康で幸福な生活)の視点から、より良いコミュニケーション支援のあり方について検討します。研究指導では、エピソード記述を用いて当事者と支援者、家族、社会との関係性の在りようを質的に吟味し、支援する側の在りようも対象とした検討を行います。
言語・非言語コミュニケーション障害の脳内メカニズムに関する認知神経心理学的アプローチ
教授 永井 知代子
脳血管障害や神経変性疾患などにより、脳の一部あるいは脳内ネットワークが破綻をきたしたとき、どのようなコミュニケーション障害が生じるのかについて研究しています。特に、顔や表情認知とその障害をきたす脳領域、描画発達とコミュニケーション障害の関係などが関心領域です。研究指導では、研究プランの立て方や脳画像を含むデータの見方から、効果的な論文作成の方法までを指導します。
失語症・高次脳機能障害の評価・訓練・指導に関する分野
教授 相馬 有里
失語症・高次脳機能障害に関する基礎的、臨床的な研究について対応します。特に失語症の会話や談話の分析方法などについて指導を行います。
高次脳機能障害の評価・治療・介入、及び加齢による認知機能の低下に関する領域
教授 植田 恵
高次脳機能障害全般について扱いますが、中でも特に認知症の神経心理学的評価の枠組みと解釈、治療・介入の技法等について取り上げます。また加齢による認知機能の低下についての基礎的研究にも対応します。
小児領域の発声発語障害の評価、訓練、指導に関する分野
准教授 佐藤 亜紀子
小児の発声発語障害の中で、特に機能性、器質性構音障害に関する基礎的、臨床的な研究について取り上げます。音声の聴覚判定および機器を用いた鼻咽腔閉鎖機能の評価に関する基礎的研究についても指導を行います。
聴覚障害児の言語発達の評価に関する分野
准教授 野原 信
幼児期から学童期の聴覚障害児の言語発達、特に状況文脈の理解など語用論的な側面に関する評価について指導を行います。
地域包括ケアシステムにおける言語聴覚療法の評価と多職種連携の効果判定に関する分野
准教授 山本 徹
地域言語聴覚療法における実践研究の手法について指導します。在宅療養支援における効果判定とチーム形成プロセスの分析を通じて、現場での実践経験を適切に言語化・構造化する手法を身につけることを目指します。
小児期発症の失語症・高次脳機能障害の評価・訓練・支援に関する分野
講師 廣瀬 綾奈
小児期に発症した失語症・高次脳機能障害について対応します。当事者への評価・訓練・支援、家族支援、医療と教育・福祉との連携について指導します。
健康科学研究科 健康科学専攻 言語聴覚学分野(博士課程)
聴覚障がい児・者および盲ろう児・者のコミュニケーションとQOL、臨床発達支援に関する分野
教授 博士(人間・環境学) 黒田 生子
聴覚障害者(あるいは盲ろう者)のwell-being(健康で幸福な生活)に資するための支援について、関与観察とエピソード記述の手法を用いて吟味し、質的な研究を行います。
認知神経心理学
教授 博士(医学) 永井 知代子
後天性・先天性脳疾患により生じる認知機能障害の脳内メカニズムに関して、臨床症例に基づいた研究の方法を指導します。
高次脳機能障害の評価・治療・介入および加齢による認知機能の低下に関する領域
教授 博士(老年学) 植田 恵
認知症などの高次脳機能障害、及び加齢による認知機能の低下に関する神経心理学的手法を用いた研究について指導します。
授業科目の概要
※授業科目等は変更になる場合があります。
健康科学研究科 修士課程 全専攻共通
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学研究法特論Ⅰ | 健康科学分野、特に臨床における研究の意義と研究論文作成の一連のプロセスを理解し、高度専門職としての実践に貢献する研究方法論を学修することで、専門演習や特別研究を実施するための基礎を作る。具体的には、保健や医療領域における具体的研究例を学ぶことを通して、研究計画の立案、データ収集と分析、研究成果のまとめ方に関する知識・技術を養う。 |
| 健康科学研究法特論Ⅱ | 院生各自の具体的な研究方法は「健康科学特別研究」で研究指導教員から学ぶことになっている。しかし、異なる研究分野における研究手法など、自分の研究では学修できないような研究内容を知ることも必要である。このような観点から、本科目は「健康科学研究法特論Ⅰ」に続く共通科目として設定し、健康科学分野の研究方法と研究論⽂作成のプロセスをより深く理解し、習熟することを到達目標とする。具体的な研究例を学ぶことを通して、研究計画の⽴案、データ収集と分析、研究成果のまとめ⽅、およびプレゼンテーションに関する知識とスキルを身に付ける。 |
| 医療統計学特論 | 科学的根拠に基づく医療(Evidence-Based Medicine:EBM)を実現させるために様々な研究が行われており、その結果を判断する上で統計学はとても重要な役割を果たしている。そのため研究デザインの段階で得られるデータの性質や解析手法をきちんと考え決めておく必要がある。本講義では、統計学におけるデータ解析の基礎的な内容から始まり、主要な統計手法について講義を行い、修士・博士課程での研究における統計処理をSPSSを用いて実践する内容とする。 |
| 医療教育学特論 | 保健医療専門職として、後進育成のために必要な教育学に関する基礎的知識と教育方法を学ぶことが目的である。また、現在の保健医療福祉領域で課題となる多重問題ケースに対応するために多職種連携教育・協働について学び、リーダーシップを担うべく知識と技術の基盤を修得することも目的とする。 |
| 保健医療管理学特論 | 保健や医療サービスシステムの現状を把握するとともに保健医療に携わる医療関連職種が直面している課題について討議し、サービスシステムを説明し課題を明らかにすることができるようにする。患者ケアシステムを実行する上で不可欠なマネージメントを学び、専門的知識・技術を有効に活用できる能力を養う。他職種の医療サービスシステムを学ぶことで他職種連携についての理解を深め、多職種協働の実践に役立てる。 |
| 健康医科学特論 | 臨床現場で関わる傷病・疾患は各医療専門職により異なる。しかし、罹患率の高い生活習慣病などに関する知識は、すべての医療専門職に必要である。疾病予防や健康維持の観点からは、成長期や青年期の健康医学の理解も重要である。臨床医学分野の最新の知識を学ぶことは、自らの生涯学習として有用なだけでなく、専門職として接する患者や家族の状況を理解し、専門的判断を構築する際に役立つと思われる。 到達目標:臨床医学一般についての知識を広げ、深めることを目標とする。 |
| 医科学英語特論 | 科学的研究分野で使われる英語や医療英語は、一般的英語と異なる点がある。英会話を含め一般的英語が得意な人でも、医療や研究分野の専門英語に慣れる必要がある。専門職業人や教育者、特に研究者をめざす大学院修士課程の院生にとって、専門分野の英語文の読解や作成能力は将来必要な基礎学力である。 到達目標:この授業では、健康科学や医学医療分野の英文読解力を向上させることを主目標とする。 |
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学特別研究 | 指導教員の指導下で修士研究を行い修士論文を作成する研究科目である。2年間の概略は次の通りである。 【1年目】実施予定の研究に関する情報集積を行い、研究の目的と方法を明確にし、研究計画を作成する。研究倫理を理解し、研究倫理教育のコースを修了する。倫理審査の承認後、研究を開始する。 【2年目】研究計画に基づいて研究を遂行し、修士論文を完成させる。研究が計画に沿って進んでいることを確認し、研究結果を分析し考察を行う。研究テーマや研究方法の変更が必要になった場合は、速やかに研究計画を修正する。倫理審査申請書類の再提出など必要な手続きを行う。 到達目標:研究倫理を理解し、倫理審査申請書類の作成を会得する。研究遂行、および論文作成のための基本的スキルを身につける。研究結果をまとめ修士論文を作成する。得られた成果を関連学会等で発表することが望ましい。 |
※共通科目は、全専攻で科目名は共通ですが、それぞれの研究テーマに沿って担当教員のもと研究を進めていく科目のため、具体的な内容は各人で異なります。
健康科学研究科 言語聴覚学専攻(修士課程)
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 言語聴覚学特論 | 言語聴覚障害の基本として、健常者の言語・コミュニケーションの生涯発達について学習する。言語・コミュニケーション過程には様々な要因が関与しており、視線、表情などの非言語的要因や、話しことばの受容に関連する聴覚機能や注意機能、表出に関連する構音、語用論的問題などの言語的要因などが関わっている。それらの要因について考察し、さらに乳幼児期から老年期にいたる言語・コミュニケーションの発達とそれぞれの発達段階で出現する問題や障害、加齢変化を、生涯発達の視点から学び、言語聴覚障害研究の基礎力を身につける。 |
| 言語聴覚学演習 | 言語・コミュニケーションに関与している諸要因、さらに乳幼児期から老年期にいたる言語・コミュニケーションの発達とそれぞれの発達段階で出現する問題や障害、加齢変化に関する基礎・臨床研究について、具体的な臨床データの分析・解釈、内外の文献講読、発表、討論を通し理解を深める。 |
| 言語聴覚障害学特論 | 言語・コミュニケーションが阻害される要因として、知的・認知的発達やその基盤となる運動機能の発達、対人社会性の発達、聴覚機能の発達、摂食・嚥下機能の発達、構音の発達など発達上の問題と、言語・コミュニケーション能力獲得後に障害を受けた場合の後天性障害がある。ここでは先天的・後天的諸要因、及び個人を取り巻く環境要因、双方によってもたらされる言語・コミュニケーションの多様な諸問題について、多面的な視点から評価・分析するための最新の知識と研究方法を修得する。当事者が日常で抱える問題性も含め、個人を包括的に捉える方法論を学ぶ。 |
| 言語聴覚障害学演習 | 先天的、または後天的諸要因と個人を取り巻く環境要因双方によってもたらされる言語・コミュニケーションの諸問題を評価・分析するための様々な方法論に関する基礎・臨床研究について、具体的な臨床データの分析・解釈、内外の文献講読、発表、討論を通し理解を深める。また、具体的な臨床研究データをもとに、個人を包括的に捉える方法論を演習を通して修得する。 |
| 言語聴覚療法学特論 | 言語・コミュニケーション障害をもつ対象者に対する機能訓練の技法と訓練効果の検証法、及び障害特性に応じたAACの適用等について修得する。また、生活支援、家族支援、教育支援、就労支援の視点から、障がいをもった個人及び彼らを取り巻く人々への臨床実践のあり方や、地域社会への働きかけの方法について、効果的な実践法を検討する。 |
| 言語聴覚療法学演習 | 言語・コミュニケーション障害、その基礎となる認知機能、高次脳機能、発声・発語機能、聴覚を中心とした感覚機能の障害に対する訓練方法と訓練効果の検証法、及び障害特性に応じたAACの適用等に関する基礎・臨床研究について、具体的な臨床データの分析・解釈、内外の文献講読、発表、討論を通し理解を深める。また、リハビリテーション研究の具体例を通して障がいをもった個人及び彼らを取り巻く人々への訓練・支援の臨床実践のあり方や、地域社会への働きかけの方法論を演習を通して修得する。 |
健康科学研究科 博士課程 共通
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 健康科学特別研究 | 研究テーマの分野への理解を深め、指導教員の指導下で研究活動を行い、得られた研究成果に基づき、博士論文を作成する。また、3ポリシーを踏まえ、博士課程修了後に自らが有する学識を教授するために必要な能力を培う学修を行う。 |
※共通科目は、全分野で科目名は共通ですが、それぞれの研究テーマに沿って担当教員のもと研究を進めていく科目のため、具体的な内容は各人で異なります。
健康科学研究科 健康科学専攻 言語聴覚学分野(博士課程)
| 授業科目の名称 | 講義等の内容 |
|---|---|
| 言語聴覚学特講 | 言語聴覚障害の基本として、健常者の言語・非言語コミュニケーションの生涯発達について研究する。言語・コミュニケーション過程には様々な要因が関与しており、視線、表情などの非言語的要因や、話しことばの受容に関連する聴覚機能や注意機能、表出に関連する構音、語用論的問題などの言語的要因などが関わっている。それらの要因について考察し、さらに乳幼児期から老年期にいたる言語・コミュニケーションの発達とそれぞれの発達段階で出現する問題や障害、加齢変化を、生涯発達の視点から学び、理論的・実践的研究を行う基礎力をつける。 |
| 言語聴覚学特講演習 | 言語・非言語コミュニケーションに関与している諸要因、さらに乳幼児期から老年期にいたる言語・コミュニケーションの発達とそれぞれの発達段階で出現する問題や障害、加齢変化に関する基礎・臨床研究について理論的・実践的研究を行う。 |
| 言語聴覚障害学特講 | 言語・コミュニケーションが阻害される要因として、知的・認知的発達、その基盤となる運動機能の発達、対人社会性の発達、聴覚機能の発達、摂食・嚥下機能の発達、構音発達など発達上の問題と、言語・コミュニケーション能力獲得後に障害を受けた場合の後天性障害がある。ここでは先天的または後天的諸要因、及び個人を取り巻く環境要因、双方によってもたらされる言語・コミュニケーションの多様な諸問題についての評価・分析法について研究する。当事者が日常で抱える問題性も含め、個人を包括的に捉える方法論について理論的・実証的研究を行う。 |
| 言語聴覚障害学特講演習 | 先天的、または後天的諸要因と個人を取り巻く環境要因双方によってもたらされる言語・コミュニケーションの諸問題を評価・分析するための様々な方法論に関する基礎・臨床研究を行う。また、具体的な臨床研究データをもとに、個人を包括的に捉える方法論について理論的・実証的研究を行う。 |
| 言語聴覚療法学特講 | 言語・コミュニケーション障害をもつ対象者に対する機能訓練の技法と訓練効果の検証法、及び障害特性に応じたAACの適用等について理論的、実証的研究を行う。また、生活支援、家族支援、教育支援、就労支援の視点から、障がいをもった個人及び彼らを取り巻く人々への臨床実践のあり方や、地域社会への働きかけの方法について、理論的・実証的研究を行う。 |
| 言語聴覚療法学特講演習 | 言語・コミュニケーション障害、その基礎となる認知機能、高次脳機能、発声・発語機能、聴覚を中心とした感覚機能の障害に対する訓練方法と訓練効果の検証法、及び障害特性に応じたAACの適用等に関する基礎・臨床研究を行う。また、リハビリテーション研究の具体例を通して障がいをもった個人及び彼らを取り巻く人々への臨床実践のあり方や、地域社会への働きかけの方法論について理論的・実証的研究を行う。 |
 対象者別
対象者別 検索
検索 入学者選抜情報
入学者選抜情報 学部/大学院
学部/大学院 キャンパスライフ
キャンパスライフ 交通アクセス
交通アクセス WEBオープンキャンパス
WEBオープンキャンパス 資料請求
資料請求 インターネット出願
インターネット出願 相談/学校見学
相談/学校見学